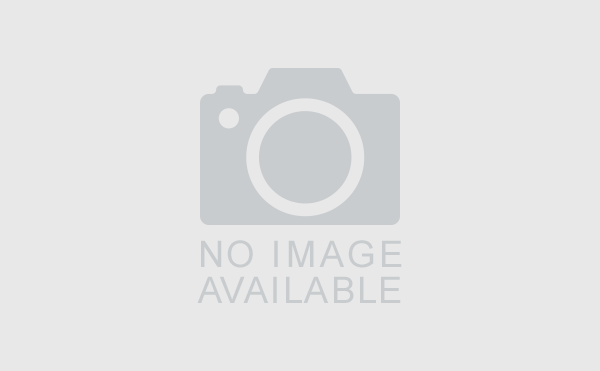業務プロセスを検討します〜効果と効率を意識
もれなく、正確に、重複しないように
監査法人の非常勤職員として会計監査に入っています。3月決算の会社は多いため、公認会計士として、繁忙期はこれからです。
さて、いま従事しているタスクは内部統制のテストですが、会社が適正な決算書を作成するためには、会社の全ての取引が
- もれなく
- 正確に
- 重複せずに
- 会社の取引として承認された取引だけが
会社の会計システムに入力されていく必要があります。
これは、社長ひとりだけの会社であっても、従業員が数百、数千、数万人規模の会社であっても、求められることです。
社長ひとりだけの会社であっても、会計システム(ソフト)への入力にあたっては、こうしたことをチェック(セルフチェック)するものですが(会社外の顧問税理士に最終チェックしてもらうことになるのでしょうが)、複数の部署や職務分掌による分業が進んだ会社では、会計システムに入力するまでの間に「複数の部署や役職者を経る長い道のり」があります。
取引の発生から会計システムへの入力までのプロセスをここでは「業務プロセス」と呼ぶことにします。
取引の発生から会計システムへの入力まで
業務プロセスは、複数のチェックの組み合わせで成り立っているともいえます。チェックとは具体的には、
- (現物と帳簿の、異なるシステム間のデータどうしの)照合:漏れや重複、不正確な転記の発見のためになされる
- (会社としての取引であることの)承認:会社とは関係のない取引や、委譲された権限外の取引の排除のためになされる
- (領収書、小切手、商品券、棚卸原票のように、財産に紐付く重要書類を管理する)連番管理:控えや管理台帳と併用し、利用履歴を管理したり、紛失や不正利用を防止したりする
などです。
これらのチェックは、
- 人手による
- システムで自動的になされる
- 人手とシステムと両方でなされる
ものがあります。
例えば、売上取引を例にすると、受注の販売管理システムへの入力に際しては、営業課員がシステムに入力するだけでは正式な入力とはならず、営業課長が同システムにログインして承認ボタンをクリックして初めて正式な入力として登録されるというぐあいです。
会計システムにインポートされるデータ候補としては、受注承認のある取引だけになるというぐあいです。実際に会計システムに売上データとしてインポートされるには、受注承認のほか、検収書に基づく検収登録と経理部の(検収書と売上データ候補の)照合も必要とするなどのプロセスを経ることになります。
さらには、営業課長の承認のない受注データをアウトプットして、営業課員に顛末をヒアリングするという「モニタリング業務」もあるわけです。
会社のチェック体制が存在することと、それが運用されていることを監査では確かめる
このような業務プロセスは、他にも様々です。入出金取引、仕入取引、固定資産(設備投資)取引、有価証券取引、経費取引、借入取引、減価償却計上、引当金計上などなど。
これら業務プロセスは会社が構築し、構築した通りに運用するものですが、会計監査では、適正な決算書を作成するための業務プロセスを識別して、これが適正に運用されていることを確かめることになります。
まとめ
かなりざっくりと業務プロセスについて触れました。適正な決算書を作成するための業務プロセスを意識することももちろん重要ですが、それは会計上、監査上だけではなく、経営上も重要です。
そもそも、適正な決算書を作成できなければ、税金の計算も誤ってしまう上、会社の経営意思決定も誤る可能性が高まります。
さらに、業務プロセスを意識して、その効果だけではなく効率を高める工夫を続け、ヒト・モノ・金・時間という限りある経営資源を有効活用することも欠かせないといえます。
日常の業務のひとつひとつの意義を考えながら、仕事に取り組んで、カイゼンとイノベーションに繋げていきましょう。

(川崎にて 満開の桜)
(本投稿の執筆時間 60分)