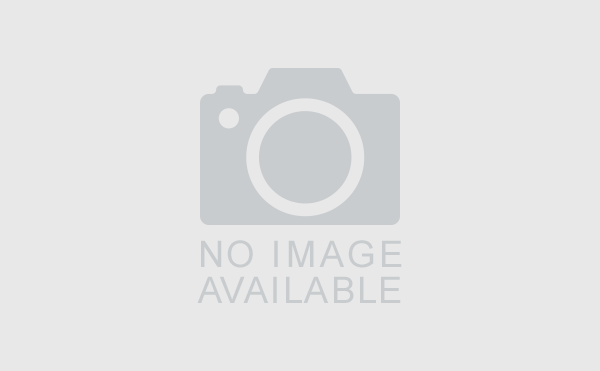ざっくり貸借対照表!
貸借対照表
会社の決算書類にも個人事業主の青色申告決算書にもあるものですが、損益計算書は穴が開くほど見るという方でも、貸借対照表はあまり見ない、それほど見ない、という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
経営がうまくいっているかどうかは、損益(儲かっているか)だけ見るのでは不十分です。儲かっていても「黒字倒産」という言葉があるように、資金繰りが行き詰れば倒産します。資金の状態がわかる貸借対照表も、損益計算書と同じような念入りさで見ておく必要があります。
貸借対照表とは
この、貸借対照表は、英語ではBalance Sheetといい、左右(右は貸方、左は借方で貸借)がバランスする表、すなわち左の縦計と右の縦計が必ず一致するという表で、決算日(ないしは、一定時点)における企業の財政状態を表現する表です。
動いている人にカメラを向けて、シャッターを切ると、そのシャッターを切った一瞬が写真になりますよね。
それと同じようなもので、常に動いている(経営されている、事業が営まれている)企業に向けて、”シャッターを切った”一瞬を捉えて、その時点の資金の状態を表すのが、貸借対照表です。

右側(貸方)は資金の調達元を示す
右側(貸方)は、上が負債、下が純資産です。
負債は、他人から資金を調達していることを意味します。期限が到来したら、返済しなければなりません。
代表的なのは借入金です。銀行などから借り入れたときには、貸方に借入金を記録します。
掛けで(支払いは後日にして)モノを買う場合の買掛金や未払金も負債です。買掛金や未払金は、直接的な借金ではありませんが、(本来であればモノの受け取りと同時に払うべきところ)支払いを猶予してもらっているという点で、お金を借りているのと同様の状態と言えます。
負債は、返済期限の早いものほど上に配置されます。(手形がないことを前提とすれば)買掛金、未払金の順に並びます。その次は借入金ですが、借入期間が一年以内の短期借入金は、一年超の長期借入金よりも上に配置されます。
純資産は、自己資金です。返済不要なものです。
このうち資本金は、元手として、企業の所有者(株主やオーナー)が企業に払い込むものです。
また、純資産のうち留保利益(利益剰余金)は、これまでに企業活動で獲得し、企業に残った利益の蓄積です。
左側(借方)は調達した資金の運用形態を示す
調達した資金をどのように運用しているかを表現するのが左側(借方)です。資産といいます。どのように投資しているかと言うこともできます。
この、資産(運用ないし投資)の並び順には決まりがあって、現金が一番上になり、現金化しやすいものほど上にきます。大まかに資産を分類すると、
- 流動資産(一番上から、現金、売掛金、たな卸資産(在庫)、その他の流動資産)
- 有形固定資産(建物、工具器具備品、車両運搬具、土地など)
- 無形固定資産(ソフトウェアなど)
- 投資その他の資産(長期投資目的の株式や債券、敷金や保証金など)
のように分類され、並び順もこの通りになります。
調達した借入金や買掛金や資本金、留保利益は、こういった資産という形になって運用(投資)されています。
重心は、左側が上に、右側は下に
これは、どう言う意味かと言うと、資産は上にくるもの、特に現金の金額を増やすことを重視し、右側は純資産を増やし、その次に負債の中でも返済期限が長いもの(長期借入金)を増やし、返済期限の短いものは減らすことを意味します。
現金は支払・決済手段として最強の資産です。現金が多ければ、いざ多額の支払いを要するアクシデントに見舞われても、企業を存亡の危機にさらさずに済みます。
総資産が多いとはいっても、建物や土地、保証金や長期の金融商品など、なかなか現金化できないものばかり持ち、肝心の現金が少ないと、いざという時に支払いができずに、企業を存亡の危機にさらすこととなります。
一方、純資産は返済が不要なので、多いに越したことがなく、負債は、返済期限が短いものが少なく、返済期限が長いものが多ければ、それだけ資金に余裕が生まれます。
返済期限が短いものが多ければ、資金繰りが厳しくなり、特に現金がそれに見合う額を用意できなければ、支払いが滞り、企業を存亡の危機にさらすこととなります。
まとめ
貸借対照表の「バランス」はとても重要で、うまくバランスが取れていないと、資金繰りが行き詰まってしまいます。
人間の重心は、左右のバランスが大事と言えますが、企業の貸借対照表の重心は、資産は上、負債・純資産は下という、左上と右下の「バランス」が重要になってきます。
貸借対照表を穴が開くほどよく見て、資金のバランスをとっていきましょう!
(本投稿の執筆時間 60分)